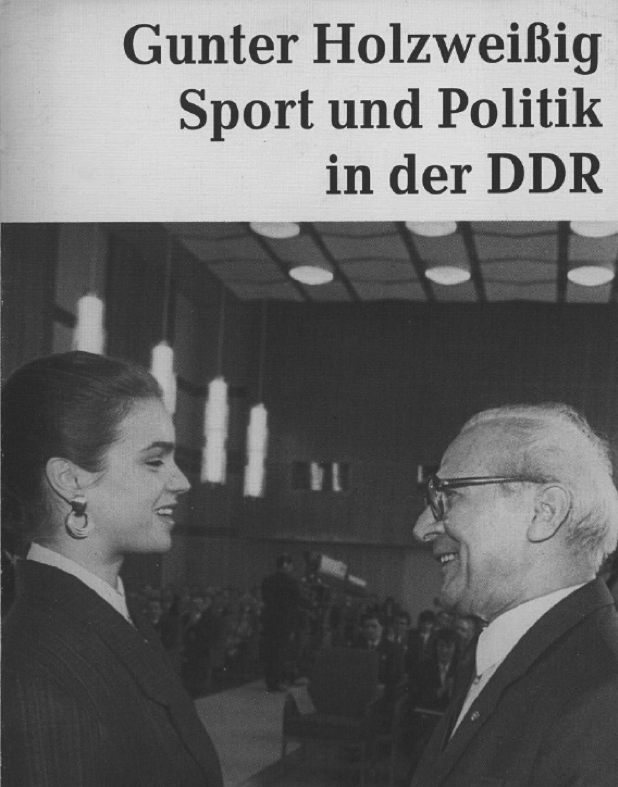はじめに
プロサッカーの香川真司選手が、2018年現在所属しているドイツブンデスリーガ「ボルシア・ドルトムント」の正式名称は、「BVボルシア09e・V・ドルトムント(Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund)」である。「ボルシア」はラテン語でプロイセン、09はクラブの創設年である1909年、「フェアアイン」(Verein)は結社あるいは協会と訳されるクラブや団体を指す。e・V・(eingetragener Verein)は登記社団、つまりドイツ民法上の「権利能力のある社団」を意味し、これによりスポーツ施設建設等のために起債や信用をはじめ、各種減免制度、自治体の補助等を受けることが可能となる。スポーツクラブは、ドイツにおけるフェアアインとして法的に認められ、こうした利点を行使できるのである。
もっとも、社団が法治国家の枠組みを前提として権利能力を取得できるがゆえの制約も存在する。例えば、登記申請をした社団に対する区裁判所の検査に際し、提出された登記書類や定款における社団の目的または活動が刑法、あるいは憲法上の秩序または国際協調という考え方に反する場合、結社は禁止されると謳われているように、社団が法秩序を遵守すべきことは当然と見なされるのである。
ところで、フランスの政治学者アレクシ・ド・トクヴィルは、19世紀アメリカにおける市民的結社の中で育まれた道徳的自己陶冶と自己抑制を、専制政治に対抗する「民主主義の学校」として評価した。結社好きの人びとは、規約の制定や投票の権利、演説の自由、目標を自分たちで決める自由、あるいは会員間の争いごとの解決方法等を市民的結社の中で育んだのだ、と。ドイツにおけるフェアアインは、まさにトクヴィルがいう「民主主義の学校」であり、私流にパラフレーズすれば、これこそがJリーグの「百年構想」で強調された地域に根差したスポーツクラブという理解の根底に流れている思想である。「民主主義の学校」にはしかし、歴史を俯瞰すれば、道徳的、宗教的、階級的、人種的、ジェンダー的排除も存在し、ある排除が新たな対抗的結社のうねりを作りだしていくこともあった。また、ドイツでは、国家が市民社会を包摂して統治する社会国家(Sozialstaat)、ならびにナチズムや東ドイツという一党独裁体制も経験している。
本章では、このような問題意識を念頭にドイツにおけるスポーツとスポーツクラブの歴史をたどりたい。
1.トゥルネンの誕生
ヤーンのトゥルネン
現在の体操競技は、床、あん馬、吊り輪、跳馬、平行棒、鉄棒、平均台などによって構成されているが、その母体となったのは19世紀のドイツで誕生したトゥルネン(Turnen)である。トゥルネンは、スウェーデン体操やデンマーク体操と並び世界的に普及していることから「ドイツ体操」とも呼ばれているが、そこには徒手体操だけでなく、疾走、縄跳び、さらには水泳やレスリングまでもが含まれており、体操の範疇をはるかに超えている。こうした実態をふまえて、本章では体操ではなくトゥルネンとそのまま表記し、その実践者もトゥルナー(Turner)と呼ぶことにしたい。
「トゥルネンの父」と呼ばれている人物がいる。ナポレオン戦争下、1811年にベルリン郊外のハーゼンハイデにトゥルネン場を開設したフリードリヒ・ルートヴィヒ・ヤーンである。ヤーンは、ナポレオンの支配からの解放と民族の統一をめざし、青年たちの愛国心の養成と体力の育成のためにトゥルネンの普及運動に身を投じた。ヤーンの功績については戦後の東ドイツでも高い評価がなされており(図1)、彼ゆかりの都市には今でもヤーンの名が冠された通りがある。
ヤーンのトゥルネンは任意会員制、会費の徴収、会員記章、服装ならびに兄弟愛的な平等性の重視、実地指導者による指導等、19世紀中頃以降に結成されていく市民的結社の原型を形作っていた。ヤーンは、ドイツの教育家ヨハン・クリストフ・グーツムーツの身体運動に学びつつ、エリート的寄宿学校の体系的授業の堅苦しさ、身分や職階制の秩序、社会の硬直した社交様式、ナポレオンの支配によって分裂したドイツ、貴族エリートによる民衆支配を批判し、トゥルネンの集団の中で平等に育まれるべき「男らしさ」と道徳的な自己陶冶を重視した。トゥルネンはヤーンの人脈を通じて、またプロイセン政府との友好関係の下で広がりを見せ、弟子たちをドイツの各都市へ輩出したものの、カールスバートの決議(1819年)により状況が一変、ヤーンのトゥルネンは存続を絶たれることになった。
トゥルネン協会の結成
プロイセン国王ヴィルヘルム4世による「トゥルネン禁止」解除の勅令(1842年)は各地でトゥルネン協会が設立されるきっかけとなった。
19世紀前半の「営業の自由」とツンフト強制(同業組合による営業権の独占)の廃止に向けた動きはツンフト機能の弱体化を通じて人びとの孤立化を促し、ドイツの工業化が賃労働者化ならびに都市化を推し進め、大衆貧困等の社会問題を生み出した。ベルリンでは1830年代以降にコレラが流行し、下層貧民に対する市民層の恐怖と嫌悪を背景に、都市の安寧秩序を問題視した道徳改革や「健康」が注目されるようになり、「公衆衛生」という新たな都市行政も生まれる。また、こうした都市行政に対抗して、自由な市民的結社による公共心の涵養も主張されるようになる。国民の陶冶、福祉の源泉となり、最下層身分に属する粗野な人びとをも含めてあらゆる個人を陶冶し、倫理的に教化する母体として自由な市民的結社が位置づけられたのである。トゥルネン協会の結成も、この流れの中にあった。
トゥルネン協会に集った会員の階層は多彩であり、彼らは平等性を前提に、協会内の様々な活動や文化様式を通じて集合心性や共属感覚、さらに互酬の精神を育み様々な共済制度を活用した。会員の収入を考慮した入会金と会費設定、遍歴職人に対する協会の印章が押された身分証明書の作成と入会金と会費減免もその一例である。しかも、身分に関係なくひとり1票制の議決権は、いまだ普通選挙制度が確立していない時期にあって、協会の平等的性格を際立たせている。
他方、会員の資格として、カード遊びの自制、道徳的に秩序づけられた品格、礼儀正しい振る舞いといった行動規範が明記され、トゥルネン協会は違反者に対して除名という厳しい処分も科した。会員資格と引き換えに要請された道徳的な品行という点では、規約に定められた名誉裁判も重要である。名誉裁判とは、公権力(国や自治体)といえども切り崩すことができなかった協会固有の仕組みであり、それは会員独自の争いごとの解決手段であるとともに、名誉を通じた集団形成の観点から、会員の規範的な統合と規律を重んじ、その意味で市民的陶冶を実現する場でもあった。
ところで、トゥルネン協会における「民主主義の学校」の象徴的な事例として、協会に設置された義勇消防団の活動を挙げることができる(図2)。この消防団は遅くとも1840年代には産声をあげ、1860年代末の段階ではトゥルネン協会の約半数が団を設けていた。そもそも消火・救援活動は人命にも関わる事柄であるがゆえに、都市における究極的な秩序形成の場であり、そうした領域の一翼をトゥルネン協会が担った意義は大きい。
トゥルネン協会が消火・救援活動を担った理由として消防団との組織的な共通性が挙げられる。分団間の連携、規律、秩序、命令を重んじる消防団にあって、梯子乗り消火・救援隊、消防ポンプ隊等の複数の小隊は隊長の命令に従い有機的に連携し機敏に行動しなければならず、こうした組織のあり方はトゥルネン協会の班別活動と類似していた。また、消火・救援活動がしばしば高階にまで及ぶことから、協会で行なわれていた登攀運動を応用することができるなど、実際の活動においても優位性を発揮できたのである。ちなみに、消火・救援活動に伴う事故への対応として運用された疾病金庫は協会の共済的性格を示している。
協会の「政治的中立」と軍制改革問題
1848・49年革命の結末とその後の政治反動は、トゥルネン協会の活動にも制約を課すことになった。端的に言えば、革命的な協会の解散をはじめ革命の中で実を結んだかに見えた市民的自由を後退させたのである。例えば、プロイセンでは1850年の1月と3月に、それぞれプロイセン憲法、プロイセン結社法が制定され、規約、会員リストの提出、政治的結社への女性、児童、徒弟の加入禁止、同種の結社との連合、他団体との共同の委員会設置の禁止措置等が講じられることになった。同様の事態はザクセン結社法、さらにドイツ連邦結社法の制定を通じ各邦にも広がっていく。警察権力によるこうした異端征伐の網の目をトゥルネン協会は警戒し、トゥルナーの国外移住者・亡命者数も増大した。彼らの中から、アメリカ合衆国等でトゥルネン協会を新たに結成しパイオニアとなる者も誕生している。
もっとも、工業化の進展とヴィルヘルム摂政をきっかけにドイツ国民協会等の自由保守派、穏健自由主義勢力が台頭するいわゆる「新時代」を迎え、協会は組織統合に向けた新たな段階を迎えることになる。トゥルネン協会の全国組織、「ドイツトゥルナー連盟」(Deutsche Turnerschaft: DT)の骨格は、こうした1860年代の帝政創設期に作られたのである。それゆえ、1860年に開催された第1回ドイツ・トゥルネン青少年祭(コーブルク祭)はトゥルネンの組織統合のみならずドイツの統一運動に連なる重要な祭典と言えるであろう。コーブルク祭では全国組織の設立問題を含む12の議題をめぐって議論が交わされ、それらは第2回ドイツ・トゥルネン祭(1861年)以降の諸会議でも引き継がれていく。中でも組織の「政治的中立」と軍制改革はDTにとって重要問題であった。
「ゴータ会議」(1861年12月)において「トゥルネン協会は、いかなる政治的党派からも無条件に遠ざからねばならない。明確な政治的判断力の育成は、ひとりひとりのトゥルナーの問題であり義務である」という方針が決議される。「政治的中立」宣言とも言うべきこの文章はDTの組織原理であり、DT指導部が組織内の政治化を封じる時に引き合いに出す典拠となった。この「政治的中立」に関しては、協会の自律性を担保するという評価とともに、プロイセン中心の権威的な国家統一の下支え、あるいは後述する労働者トゥルネン・スポーツ運動の排除の手段として悪用されているという批判もなされた。
軍制改革をめぐる議論は、同時代のプロイセン憲法紛争とも関わっていた。プロイセン軍部は革命時の郷土防衛軍の独立性を根拠とした革命的混乱と軍隊の攪乱をふまえ、革命後、戦時軍隊の均質化、すなわち「軍隊の近代化」を政策実施した。陸相ローンは正規軍の大増強を軸とする「兵役法」を下院に上程しプロイセン軍の飛躍的強化を目指したが、これに対して自由主義ブルジョアジーの陣営は、国民経済における生産的労働の損失から3年兵役制に反対したのである。ベルリントゥルネン委員会がプロイセン政府に宛てた「トゥルネンと祖国の防衛体制」(1860年2月)には、兵役期間の短縮、より迅速かつ効果的な兵士養成に向けた現役兵に対するトゥルネンによる育成が挙げられている。こうしてDT指導部は、第2帝政期に入っても協会における準軍事的な兵力育成の観点から、軍事部門に関与していくのである。
2.労働者トゥルネン・スポーツ運動の展開
DT創設と傘下の協会ならびに会員数の増加は、トゥルネン協会運動の隆盛とともに協会を担う社会層の広がりと多様性をもたらした。その中には社会主義に共鳴する労働者も多く含まれていたが、ビスマルクの社会主義鎮圧法の制定(1878年)によって状況が激変する。この法律によりすべての社会民主主義的な組織や集会が禁止され、刊行物も検閲対象とされたが、青少年層の社会民主主義への感化を危惧していたトゥルネン協会、とりわけDT指導部にとってはむしろ追い風となった。皇帝に忠実な「祖国の防塞」を自認していたDT指導部は、こうした労働者会員に対する協会からの追放、排除を支持したのである。「祖国を喪失した手工業職人、労働者はDTの中に居場所はない」。こうしたDT指導部の主張は前述の「政治的中立」宣言の精神に反し、皇帝への忠誠を誓うものに他ならず、ドイツ帝国とDTが一体のものであったことを示すものである。
社会主義鎮圧法の失効(1890年)後、多くの労働者がDT傘下の協会から脱会し、独自に協会を設立し始めた。1893年5月には「労働者トゥルネン同盟」(Arbeiter Turnerbund: ATB)が創設され、機関紙として「労働者トゥルネン新聞」も刊行された。ATBは、「DTに所属している労働者たちよ。(略)道理のない道具として悪用されることを拒否しよう。立ち上がれ、われわれとともに闘おう!」などと呼びかけ、DTによる執拗な妨害にもかかわらず、第1次大戦前に傘下の協会数、会員数を大幅に増大させた。「社会民主主義はわれわれの青少年からあらゆる道徳的なよりどころを奪い取る」というDT指導部の嘆きは若き労働者に対するATBの影響力の大きさ、特にその教育的機能の浸透ぶりを示している。それは、会員同士の共同性や連帯、帰属意識、社会的承認といったDTでも重視されていた事柄だけでなく、労働者の経済的、社会的困難を問題視したATBの取り組みがもたらしたものであった(図3)。この点と関連し、ATBは防衛能力を備えた青少年の育成をDTと同様に重視したが、単なる身体ならびに精神能力の強化ではなく、そこには高度に工業化された社会で働く青少年の経済的苦境を直視し、長時間労働、低賃金の是正といった労働運動との結合も含意されていた。

図3.労働者トゥルネン協会のトゥルナーの遠足(1890年)。「労働者トゥルナーは自由、平等、友愛のために常に闘う」と記されている。
Eichel, W. u.a., Illustrierte Geschichte der Körperkultur, Bd.1, 1983 Berlin
これらは「民主主義の学校」としての労働者トゥルネン・スポーツ運動の性格を物語っている。ATBの活動は、DTと異なっておらず、徒手体操やマスゲーム、器械運動に加え、サッカー等のスポーツ競技会も開催している。しかし、それは「労働者スポーツ・身体育成中央委員会」(ZK)の書記であったフリッツ・ヴィルドゥンクが「身体運動は、一方で労働者の健康を高め、病気から遠ざけ、それによって完全に自然な方法で人生の幸福をもたらし、他方でより高度な人生の幸福は健全な思考・生活様式へと行き着くべきであり、また悪い習慣からの回避を自明なものとするべきである。(略)このことは、すべての労働者階級がその経済的解放を同様なテンポで実現するときのみ現実化されるのである」と、明確に述べているように、労働者階級の解放をめざした労働運動であったのである。ATBは第1次大戦後、会則の中に遊戯とスポーツを組み入れることで会の名称を「労働者トゥルネン・スポーツ同盟」(ATSB)に変え会員数も大幅に拡大させたが、「帝国トゥルネン委員会」(DRA)は言うまでもなく、都市におけるトゥルネン協会やスポーツクラブとの連携は拒否された。
労働者トゥルネン・スポーツ運動は、戦間期には労働者文化運動につきものの組織の分岐・対抗を招いていたが、ATSBは、スポーツの競争原理、業績原理、記録主義、貴族的なスポーツ種目や、プロスポーツにおける資本主義、さらには軍国主義、ナショナリズム、ファシズムによるスポーツの利用等に対する批判を積極的に展開した。このようにATSBは、資本主義的ブルジョアスポーツを批判する一方でプロレタリア身体文化、いわゆる社会主義・共産主義的身体文化の創造を主張した。社会民主党と親和的関係にあった穏健的、改良主義的なATSBならびにZKは、トゥルネンとスポーツを労働者の生活改善の手段として意味づけようとし、ドイツ共産党との連携を重視するグループは、それらを共産主義革命のための手段と見なした。このような路線対立は混迷を深め、1928年のATSB総会において共産主義煽動家の排除が可決され、その結果、排除された人びとによって、「赤色スポーツ統一戦線」(KG)が新たに結成されるのである。ドイツにおける労働者トゥルネン・スポーツ運動は、こうして完全に分裂することになった。
3.トゥルネンとスポーツの抗争
ドイツでは19世紀に入り、商人や企業家等を通して英国のスポーツが伝播し始め、国際商業都市ハンブルクでは、他の都市にさきがけてボートのスポーツクラブが1830年代に誕生する。もっとも、ドイツでスポーツが広く浸透していくのは19世紀末以降である。例えば、ドイツボート連盟(1883年)、ドイツ水泳連盟(1886年)、ドイツ陸上競技スポーツ連盟(1891年)といった種目別のスポーツの全国連盟がこの時期に誕生する。ちなみにドイツサッカー連盟は1900年に設立されている。
そもそもトゥルネンには体操では括れない、よじ登り、バランス、投、飛び跳ね、水泳やレスリングといったスポーツに通じる運動群も含まれていたが、ドイツにおける英国スポーツの普及は、トゥルネン協会の組織基盤ひいては身体運動としてのトゥルネンの価値を揺るがしかねず、DT指導部が外来文化としてスポーツを批判するきっかけともなった。その一方で、DT指導部は、トゥルネン協会の伝統的性格、硬直化したドリル主義、訓練的要素、さらには普仏戦争を経て国家や軍隊との関係強化を進めたことによって、人びとから反発を買うようになっていった。労働者トゥルネン・スポーツ運動はこれらの人びとのひとつの受け皿となったが、ドイツ各地に広がるワンダーフォーゲル運動に集った青年たちもまた、都市文明の退廃と倦怠、家庭や学校の束縛や規律からの解放と自由を求めスポーツクラブに加わった。今やDTは労働者トゥルネン・スポーツ運動とともにスポーツクラブとも対抗することになったのである(図4)。

図4.ヴュルテンベルクにおけるサッカークラブ(1916年
Krüger, M., Von Klimmzügen, Aufschwüngen und Reisenwellen. 150 Jahre Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport in Württemberg, Tübingen 1998
DT指導部は、愛国心、公共的精神と道徳性、国民の健康、運動の全体性等をトゥルネンの価値として主張し、スポーツの持つ個人の名誉心と賞争い、階級的上層による独占、華やかな衣装、ケガの危険、記録重視、種目の一面的性格等を批判した。それは、近代オリンピック運動への非協力と大会への不参加という行動によっても示された。近代オリンピック運動はフランスの貴族ピエール・ド・クーベルタンを中心に進められたが、パリで開催されたオリンピック創設会議(1894年)にDTは代表者を送らず、第1回のアテネ大会(1896年)にも選手を派遣していない。近代オリンピックが帝国主義段階における欧米列強のスポーツをめぐるヘゲモニー争いの性格を持っていたことに対する、当時、世界最大の体育・スポーツ統轄団体であったDTのプライドが強く影響していたように思われる。ちなみに、ドイツがオリンピックに選手を正規に派遣したのは第4回ロンドン大会(1908年)である。
DT指導部のスポーツに対する批判は、ヴァイマル共和国でも継続する。DTは1919年以降、DRAの傘下団体のひとつになったものの、単一種目に収斂しえない組織の包括性、そして何よりも歴史的正統性への自負からDRAの方針と度々対立した。例えばDTを「器械運動と遊戯のための専門組織」とするDRAの方針には従わず、DT傘下のトゥルネン協会とスポーツ団体に所属する会員の二重登録を禁止した(1922年12月)。そしてスウェーデンにならった青少年に対するスポーツ能力検定制度の導入を決定したDRAに反発して、1925年8月の総会においてDRAからの脱退を決議する。
もっとも、DT指導部は、国防力の強化と青少年に対する社会主義の浸透の防止をめざす政府や軍当局と連携しており、青年ドイツ同盟の設立(1911年)へのDTの関与はこの点を象徴している。民間団体が軍事的な活動に携わることを警戒していた軍部であったが、社会主義の影響を前にして働く青少年の組織化に向け、人気を博しつつあったスポーツを軍隊に取り入れた。DT主催のトゥルネン祭に軍将校が出席し、DTの会長ゲッツが青年ドイツ同盟の副代表に就任する。ちなみに同盟にはDTの他にも、水泳、ホッケー、自転車、ボート等のスポーツ団体、ワンダーフォーゲル、青年育成組織、学生組合、手工業者や商人の団体等が加盟し、第1次大戦直前の時点で青年の約5分の1を占めるまでになる。
4.ナチズムによる「均質化」と余暇の組織化
ヴァイマル共和国の成立により帝国結社法(1908年)をはじめ、結社の自由を制約する法律は廃止され、DRAのみならずZKに対する法人税の廃止、団体旅行の際の運賃割引等の支援がなされるようになる。加えて、立法府の中にトゥルネン・スポーツ、健康等に関する帝国身体運動促進委員会が設けられ、そこには議会の代表とともにDRA、ZKから同数の代表も加わっている。ヴァイマル共和国はユダヤ人のトゥルネン・スポーツ団体独自の活動に対しても比較的寛容であった。ナチズム(国民社会主義)は、こうしたヴァイマル体制におけるさまざまな組織の機能を国家が吸収する「均質化」を推し進めながら、トゥルネン・スポーツ団体を政治体制に組み入れるか、あるいは弾圧によって禁止し葬り去ったのである。
ナチズムのイデオロギーが「自由なプラグマティズム」と捉えられているように、ナチ体制においてトゥルネンとスポーツに関する体系だった理論が確立されていたわけではない。ただし、ナチ党の指導部にも影響を及ぼした哲学者アルフレート・ボイムラーが提唱する「政治的体育」(politische Leibesübungen)は、ナチズムとトゥルネンとスポーツの関係を知る手がかりとなる。「政治的体育」とは、個々の身体は個人に帰属するのではなく民族全体の身体でなくてはならず、身体と精神は民族への奉仕という点においてのみ価値を獲得するというものである。それゆえ個別化を招くスポーツは拒否される。歴史的な共同体の中で生活している人間の全体教育の不可欠な要素として「政治的体育」が重要なのであり、個別的利害を追い求めるスポーツは退廃の極みとされる。このようなボイムラーの主張は、トゥルネンとスポーツの抗争の中でDT指導部がスポーツに対して浴びせた批判とも重なる。もっとも「政治的体育」は単なるスポーツ批判ではない。そこでは戦争による世界支配の実現のために、鍛え上げられ、国防能力に秀でた兵士の養成が目指され、その際、人種的、民族的優越性こそが立証されなくてはならなかった。ヒトラー内閣の宣伝相ゲッベルスが負けるはずのない非征服民とのスポーツ対戦を禁止した理由もここに由来する。国民すべての身体を全面的に強化する点で「政治的体育」は「平等」でなくてはならないが、その際の「平等」は優生思想に根ざしており、ユダヤ人をはじめ障がい者やジプシー等のマイノリティーを排除する根拠にもなっていた。
このような論理をベースにしてトゥルネンとスポーツはナチズム体制において「均質化」される。この任務を担ったのが突撃隊のハンス・チャンマー・ウント・オステンである。彼は1933年4月に帝国スポーツ委員、同年7月に帝国スポーツ長官に就任し、翌年1月から「帝国ドイツトゥルネン同盟」(DRL)、1938年からは「国民社会主義帝国トゥルネン同盟」(NSRL)という中央機関を司り、この間、国内オリンピック委員として1936年のガルミッシュ・パルテンキルヘン冬季五輪とベルリン(夏季)五輪を成功へと導いた。彼は「ドイツスポーツの新秩序」の下に「均質化」を推し進め、その結果、固有なイニシアティブと民主主義に依拠した協会とクラブの組織原則は失われ、労働者トゥルネン・スポーツ組織は禁止、共産主義的赤色スポーツ組織は容赦なく迫害され、ユダヤ人スポーツ愛好家は他の何百万人ものユダヤ人とともに絶命収容所に送り込まれたのである。
もっとも、「均質化」は必ずしも強制的に進められたのではなく、トゥルネン・スポーツ団体がナチ権力に同化しようとしていた点も指摘しておかなくてはならない。DTはチャンマーが帝国スポーツ長官に就く以前の1933年5月段階でDRAの解散を願い出ており、また遅くとも同年7月までに「完全なるアーリア人化」を傘下の協会に要請している。この時期に開催されたシュトゥットガルトのトゥルネン祭には、チャンマーとともにヒトラーも来賓として招かれ、ヒトラーは開会式の挨拶の中で、ヤーンを革命運動の先駆者として評価しナチズムの系譜に位置づけた(図5)。DT指導部は祭典を通じナチズムとDTの一体化を演じてみせたのである。DTは1936年、コーブルクにおいて解散を決定し、約70年の歴史に幕を降ろすのである。

図5.シュトゥットガルトのドイツトゥルネン祭(1933年)における少女たちの行進。来賓席の背後にはナチ党のハーケンクロイツの旗が掲げられている。
SPORT : SCHAU. Deutsche Turnfeste 1860-2002, Leipzig 2002
ところで、ナチズムは組織の「均質化」だけで支持基盤を強化したのではない。むしろ、政治やナチズムを敬遠し、非政治的な領域や私的空間へ逃げ込みをはかろうとした者のソフトな取り込みも心がけた。「歓喜力行団」(KdF)の活動はナチズムのソフト戦略のひとつであり、政治から自由な空間を創出しつつナチ体制への合意を形成するための役割を果たした。KdFは1933年5月に創設されたドイツ労働戦線(DAF)の下部組織である。ナチスの政権獲得にともない労働組合は禁止・解体され、その代替組織としてのDAFは、労働者の自発的な同意調達の手段としてKdFを位置づけた。KdFは「労働の美」「宵の余暇」「ドイツ民族教育事業」「旅行・ハイキング・休暇」「スポーツ」の各部門によって構成されており、補助金を通じて労働者等に演劇、音楽会、展覧会、スポーツ、ハイキング、ダンス、映画、成人教育等を提供したが、とりわけ補助金付旅行制度は「無階級社会」の実物宣伝であった(図6)。
KdFには、1933年から1936年の間に活動費として5600万マルクの予算が投じられ、1938年には全労働者の半数が娯楽に参加し、有給休暇も1934年時点で15日間取得することができたという。KdFは、大管区、管区、地方、拠点の4つに区分され、大管区のスポーツ局にはスポーツ医療相談所も併設された。スポーツコースには基本コースと特別コースが設けられており、すべての人びとに開かれたコースプログラムが用意された。労働者を含む多くの市民は安価な年間登録料と参加費だけでコースに参加した。基本コース(水泳、軽体操、遊戯等)では、「楽しさ」「自由」を前面に、日々の労働から解放された労働者が自由な活動領域をえて生活の喜びを感じとること、すなわち自然な新しいスタイルの生活形態を創出することが重視された。また、当時の最新のメディアであったラジオを通じた「朝の体操」や「主婦の体操」、「旅行・ハイキング・休暇」部門と連携したバルト海沿岸での「海岸スポーツ」、さらに新時代を象徴するアウトバーン労働者のための「工事宿舎でのスポーツ」も実施された。
特別コース(陸上競技、自転車、ボート、乗馬、テニス等)は、「貴族的」と見なされていた特権的なスポーツにもサラリーマンやブルーカラー労働者も参加することができ、ステータスの上昇を夢見ることができた。「労働者を強大な組織の中に追いやり、そこに埋没させること、彼らの個性を剥奪すること、一緒に進軍させ、歌わせ、歩かせはするが、決して一緒に考えさせはしない」というドイツの歴史家フランツ・ノイマンの指摘はKdFの性格を見事に言い当てている。余暇・スポーツが人びとの私的空間の深部にまで浸透したがゆえに、人間生活のすべてに対する全面的な統制が可能となったとも言えよう。人びとは不利益から社会的に保護されることによって、自分の生活以外には無関心となり、政治的なものや公共性を見失う。しかもこうしたソフトな介入は、一方で医療体操やスポーツの実践を通した健康への「権利」を万人に保障しながら、他方でそれを梃子に人びとに対して規律訓練を課し、労働力の増進という価値やナチズムへの支持を内面化していく役割を担っていたという事実を見逃してはならない。
5.分断国家ドイツのスポーツとスポーツ体制
第2次大戦後、ドイツは4連合国(アメリカ、イギリス、フランス、ソ連)による占領地区に区分され、それぞれの占領政策のもとに統治された。占領に際しては非軍事化、非ナチ化という基本目的は一致していたものの、個別政策の具体化に際しては、とりわけソ連占領地区とそれ以外とでは対照的であった。端的に言えば、ドイツの弱体化に固執するフランスの思惑もあったが、西側3地区においてはマーシャル・プランに象徴されるように、資本主義的なヨーロッパの経済協力体制の構築が目指されたのに対し、ソ連占領区では土地改革、教育改革、企業・銀行の国有化などが徹底され、ソ連による社会主義体制化が鮮明となる。こうした差異は、西側地区の通貨改革、ソ連による西ベルリン封鎖という対立と抗争を経て、最終的にドイツ連邦共和国(通称、西ドイツ:1949年5月成立)とドイツ民主共和国(通称、東ドイツ:1949年10月成立)というふたつの分断国家の誕生をもたらした。東西の対立はスポーツの領域にも持ち込まれ、ドイツのスポーツは分断国家の枠組みの中で展開されることになる。
西ドイツのスポーツ
連合国による「スポーツの政治的浄化」、すなわち非軍事化と非ナチ化は、占領政策の共通の指針であったが、1950年に唯一の全国組織(州連盟と種目別連盟)として設立された「ドイツスポーツ連盟」(DSB)は、こうした占領政策の中で、「党派的政治的中立性」、「スポーツの自主管理(自主的市民のイニシアティブ)」、「スポーツの政治的自治」、「スポーツの統一性」を基本方針にスタートした。それは連邦政府等からの各種助成を可能ならしめた「パートナーシップの原理」とともに、スポーツがもつ公共的性格を踏まえ、それをスポーツ政策として支援する西ドイツのスポーツ体制の特徴を示している。もっとも、会長ヴィリ・ダウメがDSBを政治的・思想的立場を捨象した大衆組織であると説明しているように、DSBは戦後西ドイツの資本主義復活を前提とし、かつての労働者トゥルネン・スポーツ運動やそれと結合した政治要求、あるいは対抗文化の形成とも訣別したのである。この方針は分断国家の中で強く意識された。なぜならば、東ドイツの国家的スポーツ機関や「ドイツトゥルネン・スポーツ連盟」(DTSB)が戦前の労働者トゥルネン・スポーツ運動の継承者を自負し、DSBの非政治的スタンスを反ファシズムの観点から痛烈に批判したからである。
1969〜74年の社会民主党のブラント連立政権下では、人間的な労働や生活環境を政策目標とした国内改革「構造政策と空間秩序」を通じて、余暇・スポーツが政策の一環として推進された。DSBは、こうした余暇・スポーツ政策を通じて、教育・健康・青少年問題・労働・都市政策等と有機的な関係を強めながら、包括的な「総合社会政策」の一翼を担うことになった。日本にも影響を与えたゴールデンプラン、トリム運動が政策化され、いわゆる市民スポーツが大きく発展したのもこの時期である。また、ドイツ労働総同盟(DGB)の労働時間の目標設定や「連邦休暇法」の制定には、資本側の「労働力の回復と再生」の視点を孕みつつも、市民社会における余暇の受け皿としてのスポーツクラブへの期待が込められていた。加えて、ブラント政権下では東ドイツとの関係においても東方政策による緊張緩和路線が採用され、東西ドイツ間でとりわけ競技スポーツ面での交流も生まれた。
この時期には、競技スポーツの高度化と国家支援をめぐるDSBを含む西ドイツスポーツの構造転換とも言うべき問題も顕在化していた。それは、スポーツの私事性あるいは自主管理的なスポーツから国策的なスポーツへの変化をめぐる論争であり、歴史的に育まれてきたスポーツにおける自由なイニシアティブをめぐる理念問題でもあった。DSBは「ドイツ・スポーツ憲章」(Charta des deutschen Sports:1966年)を決議した際、スポーツの国民的・社会的な課題を担うという意思表明をしているが、これはDSBの社会政策的役割の自認に他ならない。ドイツのスポーツクラブは、一方で「補助性(自治助成)原則」によってスポーツの公益性に基づく公的支援の根拠を獲得し、財政支援、土地利用、施設保有等の面でメリットを手に入れ、スポーツを通じたコミュニティーの形成に貢献してきた。しかし、他方でスポーツの自主性や自由な市民のイニシアティブという基本原則との関連からすると、国家とのパートナーシップはスポーツへの国家的関与を意味し、DSBは規約で国家の不介入・不干渉を宣言しながら、自ら国家の介入を求めるという矛盾に陥っている。こうした批判がDSBに向けられたのである。この点は、とりわけベルリンの壁建設後にステートアマチュアとして君臨し始めた東ドイツのメダル量産への対抗として登場した競技スポーツ政策の中で、より鮮明になる。
1972年のミュンヘン五輪を前に、西ドイツではホスト国としてのメダル獲得を目指したスポーツの支援体制の議論が浮上した。そこでは、東ドイツを模範としたスポーツ科学体制の国家的支援の必要性も語られ、内務省管轄の連邦スポーツ科学機関が設立、さらには連邦国防軍(スポーツ中隊、連邦スポーツ学校)による競技スポーツ支援などもなされるようになる。スポーツクラブの世界にアスリートの早期発見、エリート育成を目的とした専属トレーナーの配置等もなされた。こうした競技スポーツに力点を置いた政策に対しては、クラブや教育関係者から、自由で自立的なスポーツクラブの基本原則からの逸脱、クラブ名誉職のボランタリーな活動の否定、東ドイツ流の競技スポーツの道具化や選手の「飼育」、民族的な遊戯や運動を重視してきた協会の歴史的伝統からの乖離といった厳しい批判がなされ、西ドイツのIOC委員でもあったゲオルク・フォン・オペルのように、広範な市民スポーツこそ重視すべきだという反論もなされたのである。
さらにラディカルデモクラシーの論者からは、このようなスポーツの国家的支援と管理に対して、西ドイツの新自由主義が、スポーツ活動の自由と任意性の尊重を形骸化し、市民社会が国家の調整システムの中に組み入れられており、こうしたコーポラティズム的、官僚的な利益組織、資本主義的文化産業によって支配された「公共性」は社会の真の民主化の枠組みとは言えないという疑念や批判が発せられている。
東ドイツのスポーツ
東ドイツのスポーツは、常に社会主義の基本目標から演繹的に説明され、ライプツィヒの身体文化大学教授ギュンター・ヴォンネベルガーが定式化したように「社会主義的身体文化」、すなわち「社会主義的ヒューマニズムを刻印した、真正の、人民の身体文化」と捉えられた。そして社会主義統一党(SED)とドイツトゥルネン・スポーツ連盟(DTSB)が一体化して「社会主義的身体文化」としてのスポーツの振興が謳われた。その中にはすべての勤労者の大衆スポーツ、資本主義的弊害のない競技スポーツ、社会主義教育と平和教育、社会主義的国際協調と国際理解、女性の同権という、今日でも重視されるべき「スポーツ権」をはじめとする、スポーツに関する大切な理念が盛り込まれていた。問題は、こうした基本目標が現実の社会の中で実現されていたかどうかである。
東ドイツでは、西ドイツのような協会やクラブは言うまでもなく、ホーネッカーらかつての労働者トゥルネン・スポーツ組織の担い手が国家指導部に登用されたにもかかわらず、戦前の労働者トゥルネン・スポーツ協会すら再生されなかった。この点で、東ドイツのスポーツが市民の自由なイニシアティブによるスポーツクラブを基礎に発展してきた西ドイツと様相を異にしていることは言うまでもない。もっとも、DTSB傘下の「スポーツゲマインシャフト」が、ベルリンの壁崩壊直前の1988年段階で1万7000余り(人口10万人あたり11・5)と、西ドイツの6万2000(同10・0)とほぼ同水準であった点は、東ドイツの市民スポーツの隆盛を示しているようにも見える。
しかし、社会主義的身体文化の優位性として位置づけられたスポーツ権の保障に関しては、理念と現実との乖離があまりにも大きかった。女性の同権にしても伝統的な性別役割分業の残滓もあり、東ドイツではスポーツに限らず実現されたとは言えない。SEDを頂点にした上意下達の東ドイツのスポーツ体制において、西ドイツのような市民のイニシアティブの場は残されておらず、最重要視されたのは国威発揚のための重要な手段となった競技スポーツの推進であった。東ドイツは1960年代以降、競技スポーツ強化=金メダル獲得を方針化し、サラエヴォ冬季五輪(1984年)では金メダル数で世界トップの座を獲得するにいたる。こうした競技スポーツの実績は、同時代の西ドイツのスポーツ界をして、「東ドイツモデル」という関心さえを呼び起こした。しかし、世界から「スポーツ大国」として注目された東ドイツの競技スポーツには以下のような重大な問題点が存在していたことを忘れてはならない。
ひとつは、競技スポーツに限られたことではないが、スポーツが党、国家、スポーツ団体の三位一体化による監視の網の目におかれていたことである。このことは、東ドイツの競技スポーツの基幹的な組織として国家人民軍(NVA)の「フォアヴェルツ」(軍のスポーツクラブ)と国家保安省(シュタージ:MfS)の「ディナモ」(中央統率事務局スポーツクラブ)が位置づけられていた点にも表れている。NVAは軍事的鍛錬とともに、国民に対するイデオロギー教育そして競技スポーツ強化の場であった。また、1950年に設立されたMfSは、外交・軍事・通信・旅行・防諜などの部門で構成されていたが、正規の職員と多くの非公式協力者を通じて、社会の隅々に監視網を張り巡らした。例えば外交官、MfS、年金生活者のみ許された国外旅行の特典はトップアスリートにも提供されたが、アスリートたちは東ドイツの「スポーツウエアを着た外交官」として期待されつつ、スポーツ界の反逆者をあぶり出すために厳重に監視されたのである。シュタージの資料を用いて監視の実態を赤裸々に記した、カルガリー五輪女子フィギャスケート金メダリストのカタリーナ・ビットの回想録は、この点を雄弁に物語っている(図7)。
もうひとつは国威発揚の帰結として競技スポーツの強化=金メダル獲得に向けて、党、国家、スポーツ団体、大学、ジャーナリズム等の総力を結集した非科学的、非人道的ドーピングが常態化していたことである。ホーネッカー体制に入り、SED、DTSBが策定したスポーツ政策をベースに、身体文化大学や中央ドーピング研究所、労働・スポーツ医学局に所属する研究者らがドーピングの実用化=証拠隠滅に向けた「研究」を行ない、実行部隊のスポーツ組織の中でアスリートがそれを検証するという協力体制が築かれた。ベルリンの壁崩壊翌年の連邦議会で設けられた「ドイツにおけるSED独裁の歴史と結果に関するアンケート調査」委員会(エッペルマン委員会)では、成人のみならず幼い子どもにも容赦なく実施された東ドイツのドーピングの実態が告発されている。
東ドイツの競技スポーツをスポーツ選手の自由とスポーツ組織の自治を奪い取った国家的犯罪として断罪することは容易い。しかし、東ドイツのスポーツの歴史からは負の遺産しか思い出すことができないのだろうか。歴史を「可能性の幅」において捉える観点から、この問題を複眼的に捉え直す手がかりとして、ここでは次の2点に注目しておきたい。
第1に、東ドイツの民衆が歴史に刻み込んだ、ある種の「主体性」である。東ドイツのスポーツが中央集権的な体制の監視の下にあったことは間違いないが、人びとはこうした監視体制に無条件、無批判に従っていたのだろうか。東ドイツの余暇に関する最近の研究によれば、東ドイツにおいても西ドイツと同様、消費社会化の潮流の中で余暇の個人化が進行し、例えば、休暇サービスとしての旅行の際、SEDが供給する保養所に不満を抱く人びとがひしめいていた。また、ボウリングは人びとの人気を博したものの、メダルとは無縁であるがゆえに振興の対象とはならなかった。人びとは、国策とは別の次元で余暇・スポーツに親しんでいたのである。文化ポピュリズムの機制を看過してはならないが、そこには市民の「参加型独裁」(フルブルック)という視点だけでは捉えきれない「支配貫徹社会」のほころびも示されているのではなかろうか。
第2に、社会主義的身体文化の理念として盛り込まれていた「スポーツ権」である。理念と実態の間に乖離があったことは先に見たとおりだが、理念そのものの先駆性は今日改めて注目されてもよいのではないか。女性の同権を含めて、障がい者や社会的マイノリティーを含む、すべての人びとに開かれたスポーツの権利保障、そのための市民的自由権のみならず社会権をも含んだスポーツ政策は、今日ますますその重要性を増していると言えよう。
6.ドイツ統一とスポーツの発展に向けて
ライプツィヒのニコライ教会から始まった月曜の民衆デモは、またたくまに主要都市に伝播し、1989年11月にベルリンの壁は崩壊した。その後、分断国家ドイツは西ドイツによる東ドイツの併合という形で統一された。
この流れはスポーツ界にも影響を及ぼし、東ドイツのスポーツは制度上、西ドイツのスポーツの枠に完全に組み込まれた。それは、加盟組織の自主性の確保、連邦主義の組織原則、党派性の否定と政治的中立性等の基本原則といったものであり、総じてスポーツの公共性の理解に基づくものであった。東ドイツのDTSBは国家から引き離されて民間団体となったが、財政難による活動の停滞ないし中止を余儀なくされた。
統一ドイツのスポーツはどのような未来図を描こうしているのだろうか。「スポーツ・フォア・オール」の理念のもとDSBは、9万を超えるスポーツクラブ、約2700万人のクラブ会員を擁しており、さらにフィットネスなど市場が提供するスポーツ商品を購入する人びとも増加傾向にある。21世紀に入り影響を強めつつあるグローバル化した新自由主義システムの中で、ドイツ社会国家の負荷能力は限界に達しつつあり、市民的結社のパワーも自明ではなくなっている。「市民参加の道具化」が進行する現在、市民社会論の批判力の神聖化が孕みかねない病理を看過してはならず、ドイツのスポーツクラブ像もその根底から検討されなくてはならない。
加えて、近年「オスタルギー」(オストとノスタルジーの合成語)という東ドイツへの郷愁を意味する造語が注目を浴びている。これは旧東ドイツの監視社会への回帰を夢みる言葉ではないものの、21世紀に入りますます顕在化しつつある東西のまぎれもない経済格差を反映した、東に位置する市民の苛立ちと自己回復の表現である。国家パターナリズムの自明視された規範=専制を内破した人びとが直面する国民的な溝を前に、今やEUの盟主的存在となったドイツがスポーツクラブに期待する社会的機能とはなにか。かつてトクヴィルが高く評価した「民主主義の学校」としての市民的結社のありようが、あらためて問われている。